最終更新日:

頭皮の乾燥によるフケが気になっていませんか?かゆみや白い粉のようなフケは、不快感だけでなく見た目の印象にも影響します。本記事では、乾燥によるフケの原因や予防方法、適切なケアや治療法まで詳しく解説し、対策を紹介します。改善しない場合の対処法まで解説するのでぜひ参考にしてみてください。

大学卒業後、美容・健康通販メーカーに入社し、基礎化粧品やボディケア商品の企画開発業務を担当。
2020年にアンファー株式会社に転職。
2020年:スキンケアブランド「DISM」の商品開発チームにジョイン
2021年:男性ダイエットブランドの立ち上げ及び商品開発業務
2022年:男性妊活ブランド「オムテック」の立ち上げ及び商品開発業務
2023年: 「スカルプD」商品開発責任者
2024年(現在): 「スカルプD」 「スカルプDボーテ」商品開発責任者
 頭皮の乾燥によるフケとは
頭皮の乾燥によるフケとは

フケにはいくつかの種類があり、それぞれ見た目や原因が異なります。この項では、フケのタイプごとの特徴と見分け方を、以下のポイントに分けて説明します。
まずは自分のフケのタイプを知ることから始めましょう。
| フケのタイプ | 乾性フケ | 脂性フケ |
|---|---|---|
| 大きさ | 小さい | 大きい |
| 色 | 白っぽい | 黄色っぽい |
| 状態 | カサカサしている | ベタベタしている |
| 目立つ場所 | 肩口や襟首 | 頭皮や髪の毛の根元 |
 頭皮の乾燥でフケが出やすい原因
頭皮の乾燥でフケが出やすい原因
頭皮が乾燥すると肌のバリア機能が弱くなって角質が剥がれやすくなり、カサカサとした乾性フケが出やすくなります。
頭皮を乾燥させる主な原因は次のとおりです。
順に解説します。
 頭皮の乾燥を防ぐフケ対策
頭皮の乾燥を防ぐフケ対策

増えた乾性フケは襟足や肩口に積もって不潔な印象を与えます。以下で紹介する方法で、頭皮の乾燥とあわせてフケを予防しましょう。
では、頭皮の乾燥を防ぎ乾性フケを抑える対策について解説します。
 フケが改善しない場合の対処法
フケが改善しない場合の対処法
セルフケアや生活習慣の改善を続けてもフケが改善しない場合、頭皮に何らかの病気が隠れている可能性があります。放っておくと悪化する恐れがあるため、皮膚科の受診も検討しましょう。
病院に行くべき判断基準と、実際に行われる治療内容について解説します。
 頭皮の乾燥とフケの原因を知り適切に対策しよう!
頭皮の乾燥とフケの原因を知り適切に対策しよう!
頭皮の乾燥は、乾性フケの主な原因のひとつです。乾燥により角質が剥がれやすくなって、白く細かいフケが目立ちやすくなり、不快感やかゆみを引き起こします。
フケを予防するには、洗いすぎを避ける、頭皮をしっかり保湿する、加湿や食生活にも気を配るなどの対策がおすすめです。また、シャンプーの選び方やドライヤーの使い方を工夫するだけでも、頭皮の乾燥を抑える効果が期待できます。
それでも改善しない場合は、皮膚炎や感染症の可能性もあるため、早めに皮膚科を受診しましょう。自分に合った方法で頭皮環境を整えて、フケのない健やかな頭皮を保ちましょう。
 |
 |
|
| 商品名 | スカルプD 薬用スカルプシャンプー&パックコンディショナーミニパウチ | スカルプD 薬用スカルプシャンプー&パックコンディショナー |
|---|---|---|
| 価格 | 1,650円(税込) | 8,200円(税込) |
| 使用期間 目安 |
約14日分 | 約2ヶ月 ※1回2プッシュ |
| 受け取り | ポスト投函 | 宅配 |

大学卒業後、美容・健康通販メーカーに入社し、基礎化粧品やボディケア商品の企画開発業務を担当。
2020年にアンファー株式会社に転職。
2020年:スキンケアブランド「DISM」の商品開発チームにジョイン
2021年:男性ダイエットブランドの立ち上げ及び商品開発業務
2022年:男性妊活ブランド「オムテック」の立ち上げ及び商品開発業務
2023年: 「スカルプD」商品開発責任者
2024年(現在): 「スカルプD」 「スカルプDボーテ」商品開発責任者

【毛髪診断士監修】夏にフケが出る原因は?フケをなくす方法や効果的なフケ対策も詳しく解説!
最終更新日:
2025/06/30
監修者:桜庭 翔
夏のフケをなくす方法から、フケの予防法や注意点まで詳しくお伝えします。
CHECK
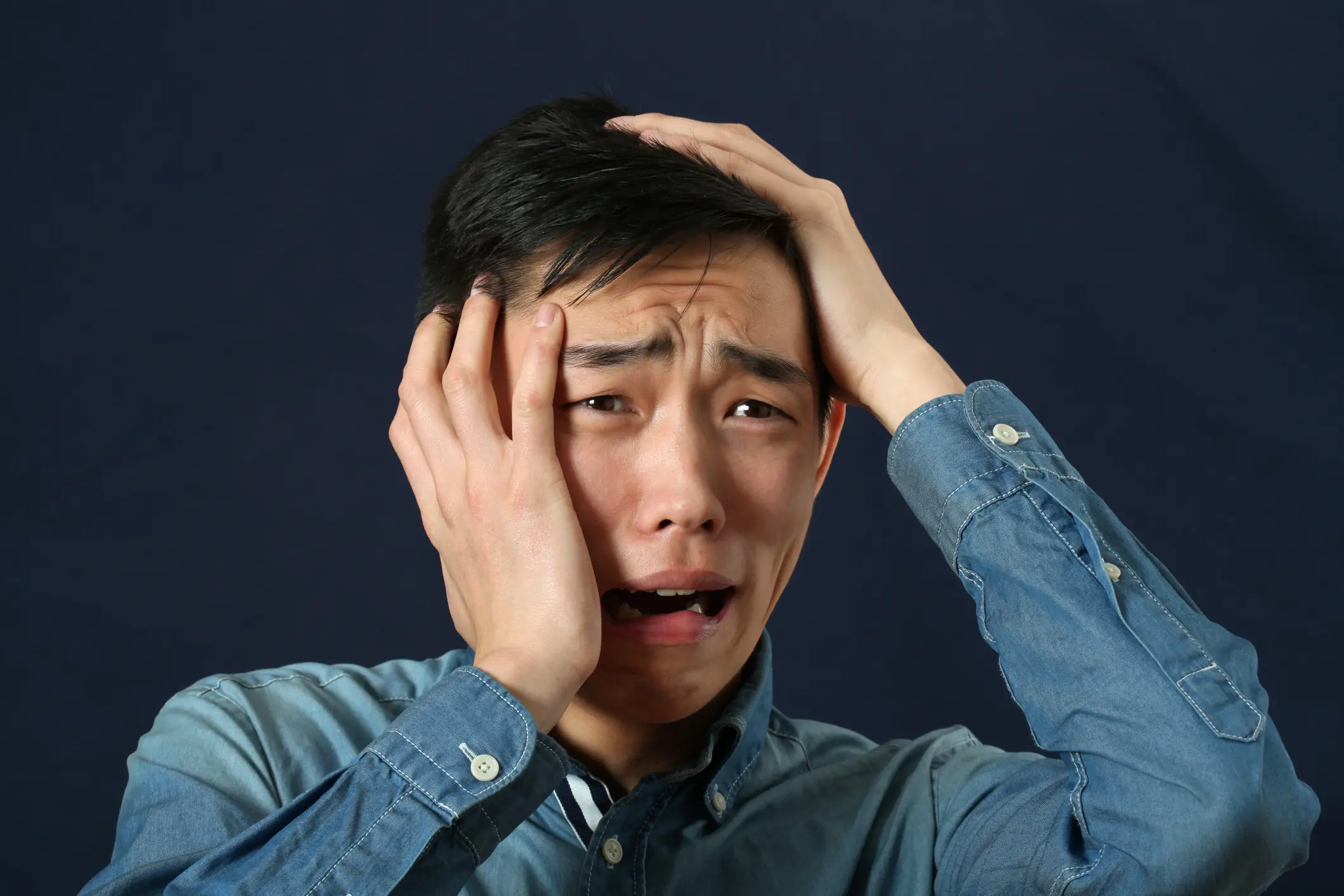
【毛髪診断士監修】薄毛対策に効く食べ物とは?毎日の食事で摂りたい食品リスト
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
薄毛(ハゲ)になる食事や食習慣、予防に効果的な食べ物や食事の方法を説明します。
CHECK
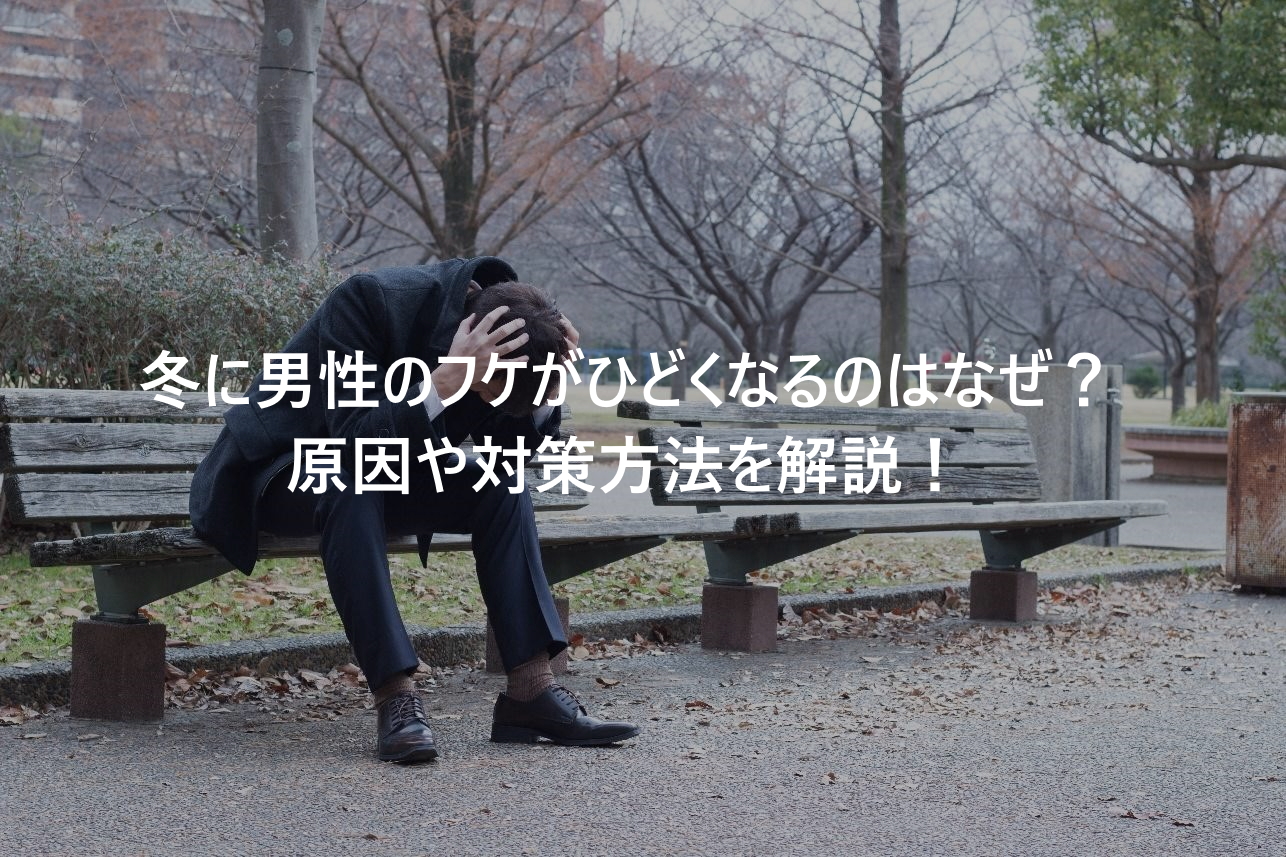
【毛髪診断士監修】冬に男性のフケがひどくなるのはなぜ?原因や対策方法を解説!
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
フケは見た目の不潔さが気になるだけでなく、頭皮や髪のトラブルサインでもあります。一時的なものだからとそのまま放置するのはNGです。そこで今回は冬のフケの原因と対策方法をご紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】髪の毛の根元に白いものが見えたら要注意!特徴をチェックして正体を見極めよう
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
頭皮や髪の毛の白いかたまりは、シラミ、フケ、ヘアキャスト、角栓のいずれかと考えられます。特徴で見分けるチェック方法、発生する原因、対策法をご説明します。
CHECK

【毛髪診断士監修】中学生で大量のフケが出る原因とは?すぐに対策できる3つの頭皮ケア
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
中学生のフケの主な原因とそれらの解消方法をご紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】産後のフケの原因は女性ホルモン低下とストレス!改善法はあるの?
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
産後のフケの原因や対策方法をご紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】髪のべたつきが気になる!べたつきの原因とその解消方法とは…
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
髪がべたつく原因や、解消方法をご紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】フケじゃない?大きいかさぶたの正体と原因!繰り返しできるのは病気かも
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
フケとは違い、かさぶたは肌のダメージを回復させる過程で生じるため、原則として剥がさないようにしましょう。本記事では大きいかさぶたへの対処方法や病気の可能性について解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】ブラッシングでフケが改善?おすすめのくし・ブラッシングのやり方
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
フケは毎日のブラッシングで改善ができるのでしょうか?この記事では、くしでブラッシングするとフケが改善する理由や、シャンプー前のブラッシングのやり方などについて詳しく解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】フケの原因はドライヤー?正しいドライヤーのやり方・そのほかの原因も紹介
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
この記事では、フケの原因になりうるドライヤーのかけ方や、フケを予防する方法について解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】フケ・かゆみの原因は乾燥と皮脂?対策にはシャンプーを見直す!
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
この記事ではフケ・かゆみの原因や対策方法についてヘアケアと生活習慣の2つの方向から解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】フケが抜け毛につながる?!フケの原因と今日からできる対策方法
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
フケが大量に出ていると、禿げてしまうのではないかと不安になることもあります。この記事では、フケの原因や抜け毛につながる可能性について解説しています。
CHECK

【毛髪診断士監修】フケが止まらないのはなぜ?乾性・脂性それぞれの原因や病気の可能性
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
通常なら目に見えないほど小さなフケが目立つ方は、頭皮環境が悪化している可能性があります。この記事ではフケの種類や止まらない原因、対処法について解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】乾燥がフケの原因に?頭皮の乾燥を防ぐ方法やその他のフケの原因を紹介
最終更新日:
2025/04/21
監修者:桜庭 翔
この記事ではフケの種類や乾燥により増えるフケを防ぐ方法を解説します。記事の後半では乾燥以外のフケの原因も紹介しているので、フケに悩んでいる方は参考にしてください。
CHECK

【毛髪診断士監修】フケは湯シャンで減る?増える?湯シャンのメリットや向いている人の特徴
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
この記事では、湯シャンのメリットや向いている人・向いていない人、やり方について解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】頭皮が脂性でべたつく…乾燥肌との見分け方は?脂性肌の原因と改善方法
最終更新日:
2025/09/30
監修者:桜庭 翔
この記事では頭皮の肌タイプや脂性になる3つの原因、および改善方法について解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】頭皮がピリピリ・ちくちく痛い!原因と対処法は?もしかして帯状疱疹かも
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
この記事では、頭皮がピリピリ・ちくちくする原因や対処法について解説します。痛みが続くときに疑われる病気も紹介しているので参考にしてください。
CHECK

【毛髪診断士監修】抜け毛の原因はストレス?抜け毛が増える仕組みや脱毛症、対処方法を紹介
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
ストレスは心身にさまざまな悪影響をおよぼし、抜け毛のリスクを高める恐れもあります。この記事では、ストレスで抜け毛がふえる仕組みや起こり得る脱毛症、および対処方法などについて解説します。
CHECK