最終更新日:

「フケを一瞬でなくしたい」「しっかりシャンプーしているのに、頭皮のフケがひどい」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。フケを一瞬でなくす方法はなく、シャンプーの方法や生活習慣の改善など継続したケアが欠かせません。一瞬でなくしたいほど大量のフケに悩んでいる方は、この記事で取り上げた対策をお試しください。

大学卒業後、美容・健康通販メーカーに入社し、基礎化粧品やボディケア商品の企画開発業務を担当。
2020年にアンファー株式会社に転職。
2020年:スキンケアブランド「DISM」の商品開発チームにジョイン
2021年:男性ダイエットブランドの立ち上げ及び商品開発業務
2022年:男性妊活ブランド「オムテック」の立ち上げ及び商品開発業務
2023年: 「スカルプD」商品開発責任者
2024年(現在): 「スカルプD」 「スカルプDボーテ」商品開発責任者
目次
 フケを一瞬でなくす方法はある?
フケを一瞬でなくす方法はある?
フケを一瞬でなくす方法として、以下のやり方が考えられます。
とはいえ、これらはあくまで一時的な対策です。あくまで「その場しのぎ」でしかないので、一瞬でフケがなくなったとしてもまたすぐに出てきます。残念ながら、フケを一瞬で、かつ永久になくす方法はありません。フケをなくすには、普段から頭皮ケアを続けたり生活習慣に注意したりすることが必須です。
 フケは頭皮からはがれ落ちた角質
フケは頭皮からはがれ落ちた角質

フケの対策を紹介する前に、なくしたい対象である「フケ」とは何かを見ていきましょう。
フケとは頭皮から出た古い角質で、通常は目に見えないサイズです。しかし、頭皮に何らかの異常が発生していたり生活習慣に乱れがあったりすると、フケの量が増える、もしくは大きなフケができることがあります。
 頭皮のフケは2種類
頭皮のフケは2種類
フケには脂性フケと乾性フケの2種類が存在します。べたつき湿っているのは頭皮の常在菌が原因となる「脂性フケ」です。乾燥している場合は、主に、頭皮の乾燥により発生するのは、乾燥した「乾性フケ」になります。
| フケの種類 | 特徴 |
|---|---|
| 脂性フケ |
・ベタベタの触り心地 ・白や黄色 ・大きなかたまり |
| 乾性フケ |
・カサカサ・パラパラ ・白色 ・小さなかたまり |
大きいフケのほとんどが「脂性フケ」です。脂性フケは洗い流すしかありません。軽い「乾性フケ」であれば、ドライヤーを使って一瞬でなくせる可能性があります。
 【種類別】フケの発生原因
【種類別】フケの発生原因
下表のように、脂性フケと乾燥フケではそれぞれ原因が異なります。
| 脂性フケ | 乾性フケ |
|---|---|
|
・皮脂が過剰分泌している ・洗髪回数が足りない ・皮脂を落としきれていない |
・頭皮が乾燥している ・洗髪回数が多い ・シャンプーの洗浄力が強すぎる |
どちらのフケも、原因の多くは頭皮環境の悪化によるターンオーバーの乱れです。ここでは、脂性フケと乾性フケの発生原因を解説します。
 フケをなくす方法と対策
フケをなくす方法と対策

頭皮のフケ対策として有効なのは、自分の頭皮状態に合った正しいヘアケアと生活習慣の改善です。具体的には、以下のようなポイントが挙げられます。
ここからは頭皮のフケを改善しつつフケをなくす方法や、フケ対策を紹介します。
 フケが改善しないときは病気かも?
フケが改善しないときは病気かも?
セルフケアを行ってもフケが改善しないときは、何らかの病気になっているかもしれません。以下で解説する病気の症状に当てはまるときは、早めに病院を受診しましょう。
 頭皮のフケに関するよくある質問
頭皮のフケに関するよくある質問

ここでは、頭皮のフケに関するよくある質問に回答します。
 フケを一瞬でなくすのは難しい!普段の生活習慣を見直し時間をかけて改善しよう
フケを一瞬でなくすのは難しい!普段の生活習慣を見直し時間をかけて改善しよう
フケは脂性フケと乾性フケの2種類に分類されます。フケを一瞬でなくすのは難しく、どちらのフケにしても、日々のヘアケアや食事、睡眠など、多角的なアプローチが欠かせません。
何から始めるか迷う場合、まずはシャンプー選びから始めてみるのもおすすめです。べたつきが気になる場合は脂性肌用のシャンプーを、乾燥が気になる場合はマイルドな洗浄力のアミノ酸系シャンプーを試してみましょう。
セルフケアをしても、一瞬でなくしたいレベルのフケが多い場合は何らかの病気を発症しているかもしれません。悪化する前に早めに皮膚科を受診しましょう。
 |
 |
|
| 商品名 | スカルプD 薬用スカルプシャンプー&パックコンディショナーミニパウチ | スカルプD 薬用スカルプシャンプー&パックコンディショナー |
|---|---|---|
| 価格 | 1,650円(税込) | 8,200円(税込) |
| 使用期間 目安 |
約14日分 | 約2ヶ月 ※1回2プッシュ |
| 受け取り | ポスト投函 | 宅配 |

大学卒業後、美容・健康通販メーカーに入社し、基礎化粧品やボディケア商品の企画開発業務を担当。
2020年にアンファー株式会社に転職。
2020年:スキンケアブランド「DISM」の商品開発チームにジョイン
2021年:男性ダイエットブランドの立ち上げ及び商品開発業務
2022年:男性妊活ブランド「オムテック」の立ち上げ及び商品開発業務
2023年: 「スカルプD」商品開発責任者
2024年(現在): 「スカルプD」 「スカルプDボーテ」商品開発責任者
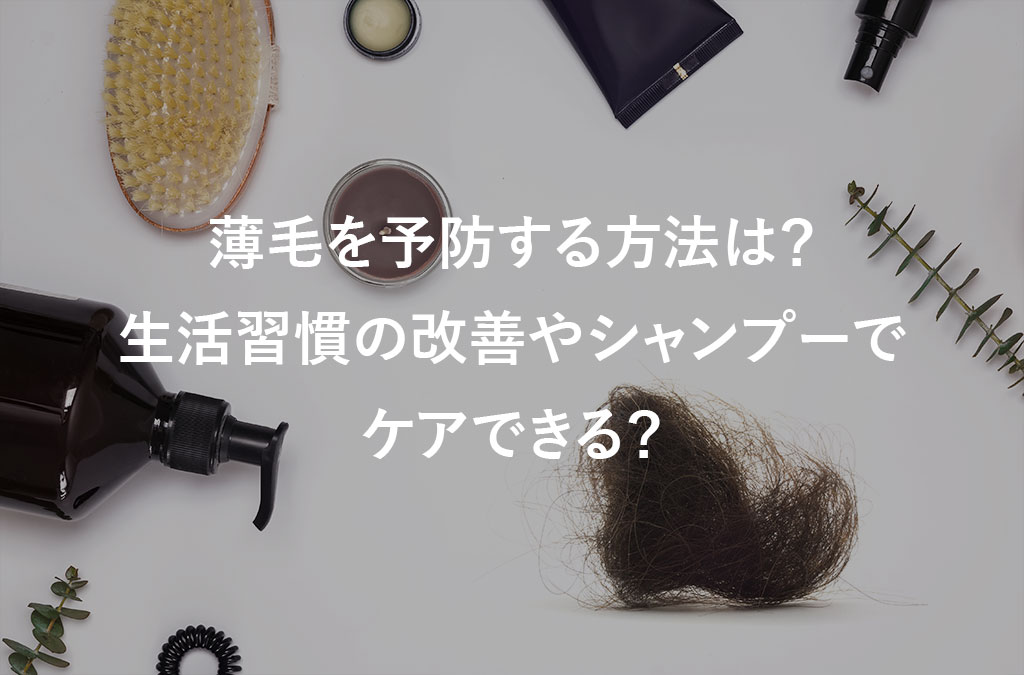
【毛髪診断士監修】薄毛の予防方法とは?改善すべき生活習慣やシャンプー、ヘアケア方法を解説!
最終更新日:
ファイルが存在しません: ../../usuge/usuge-measures/index.html
監修者:桜庭 翔
薄毛の予防・改善方法を生活習慣、ヘアケア方法の大きく2つに分けてご紹介。今の状態を知るためのチェックリストや薄毛が起きる仕組みも合わせて解説していくので、ぜひ参考にご覧ください。
CHECK
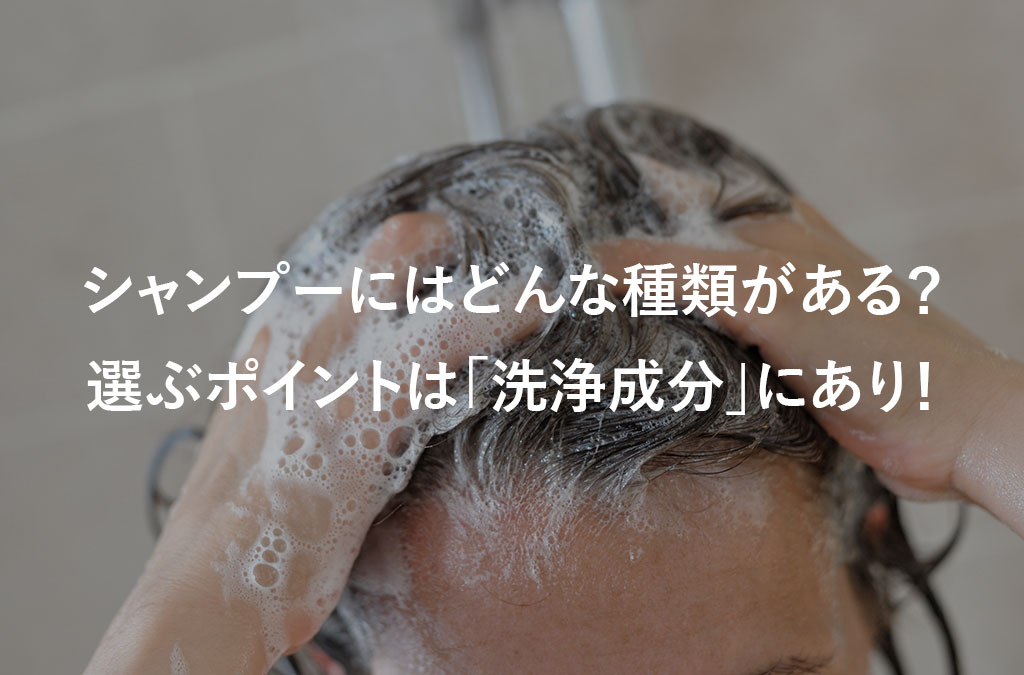
【毛髪診断士監修】シャンプーにはどんな種類がある? 選ぶポイントは「洗浄成分」にあり!
最終更新日:
ファイルが存在しません: ../../usuge/usuge-type/index.html
監修者:桜庭 翔
シャンプー選びが間違っていると、かゆみやフケ、脂っぽさ、薄毛などのトラブルが起こるかもしれません。今回は「洗浄成分」の種類について、アンファーが詳しく解説します!
CHECK
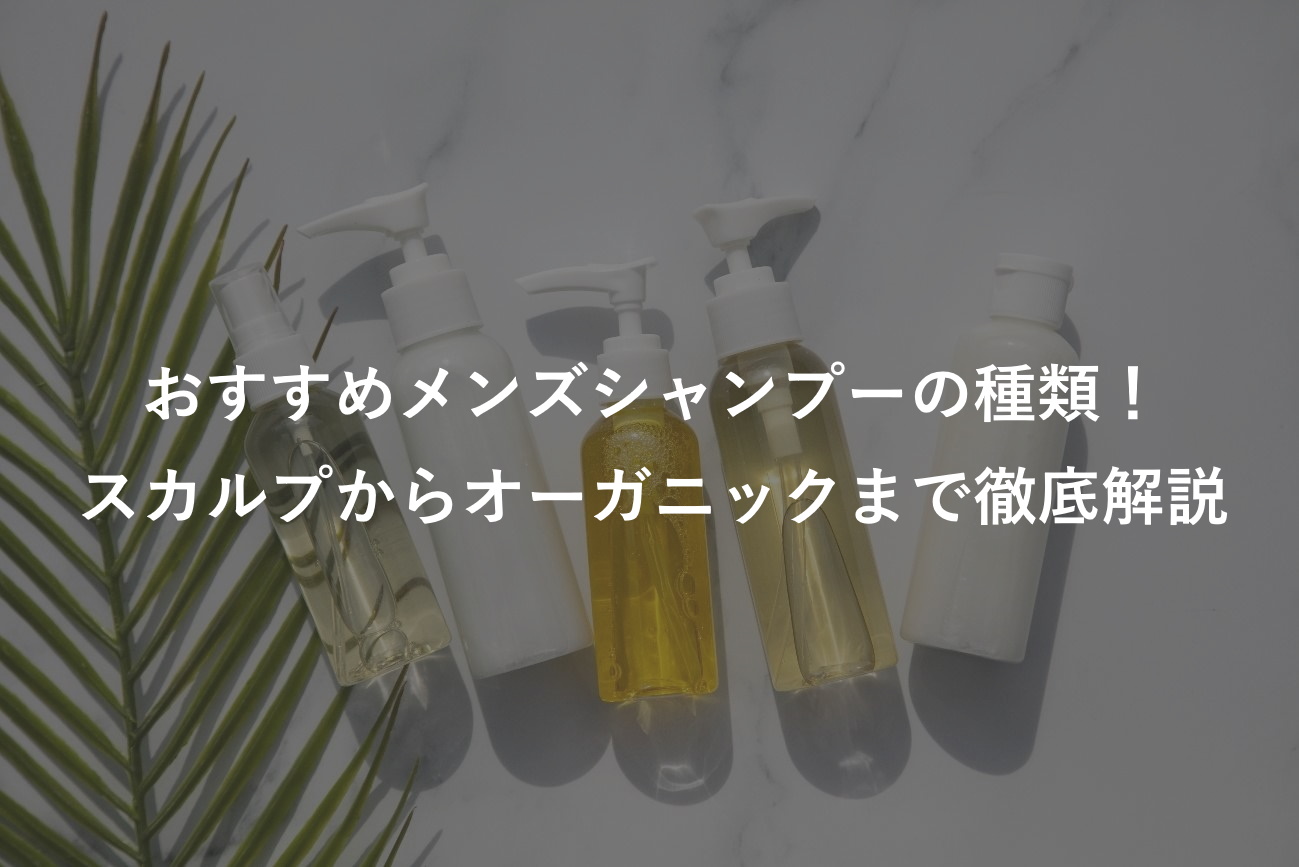
【毛髪診断士監修】おすすめメンズシャンプーの種類!スカルプからオーガニックまで徹底解説
最終更新日:
ファイルが存在しません: ../../usuge/shampoo-type/index.html
監修者:桜庭 翔
頭皮の皮脂や臭いが気になるなど、メンズシャンプーに興味を持つ男性の方もいるでしょう。でも、いざ使いたいと思っても、どれを選んだらよいのか迷うことも…。
CHECK

【毛髪診断士監修】薄毛の人は頭皮の厚みが約6mm?厚みがないと薄毛につながるって本当?対策方法を紹介
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
頭皮の厚みがないと薄毛につながる可能性があります。近年の研究により、毛量が少ない人は頭皮が薄い傾向にあると判明しました。
CHECK

髪の毛が細い原因や対策を解説!男性の髪を太く育てる方法とは?
最終更新日:
2025/03/04
監修者:アンファー株式会社
自分の髪の毛が細いかどうか知るために役立つ情報や、髪の毛が細くなる原因、髪の毛を太くする方法について解説します。
CHECK

髪に結び目ができる「玉結び」の原因は?髪へのダメージと対策法
最終更新日:
2025/03/04
監修者:アンファー株式会社
ふと髪の毛に触れたとき、わずかな引っかかりを感じて見てみたら結び目ができていた、という経験はありませんか。これは「玉結び」と呼ばれる現象です。
CHECK
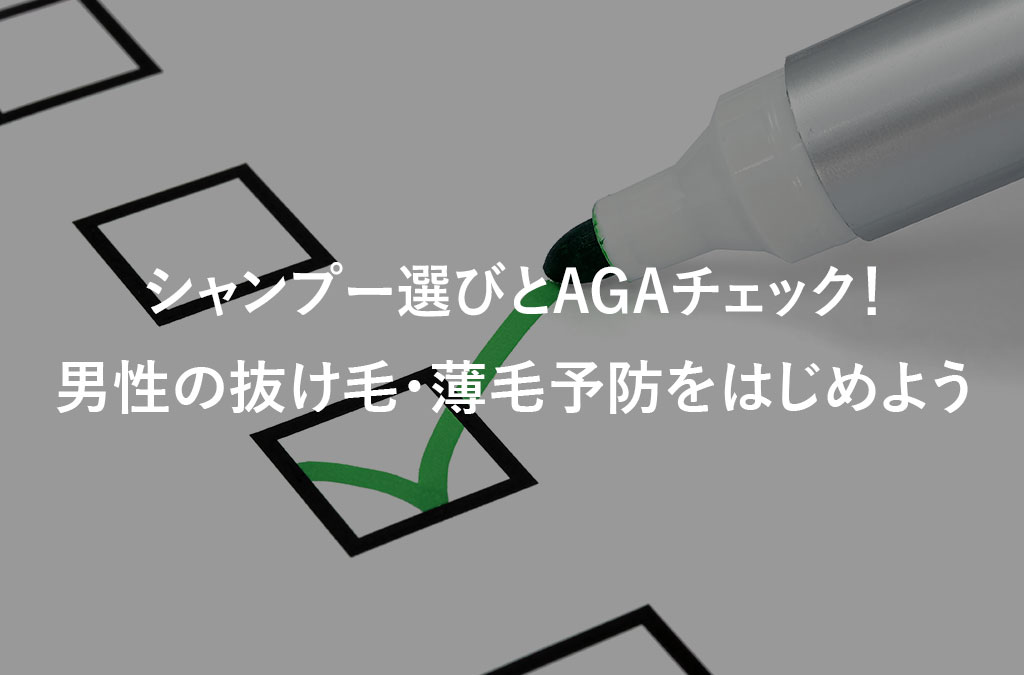
【毛髪診断士監修】男性の抜け毛予防に必要なのは、シャンプー選びとAGAチェック!
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
シャンプー選びや抜け毛対策に加えて、男性にとって気になるAGAの特徴やチェックポイント、改善方法を詳しく解説。これであなたの抜け毛対策を、万全なものにしてください。
CHECK

【毛髪診断士監修】頭のフケをなくす方法とは?シャンプー方法やヘアケアの見直しについて解説
最終更新日:
2025/05/27
監修者:桜庭 翔
フケの原因と、フケをなくすための方法を紹介します。 頭皮環境を正常に整えれば抜け毛予防にも役立つので、ぜひチェックしてみてください。
CHECK
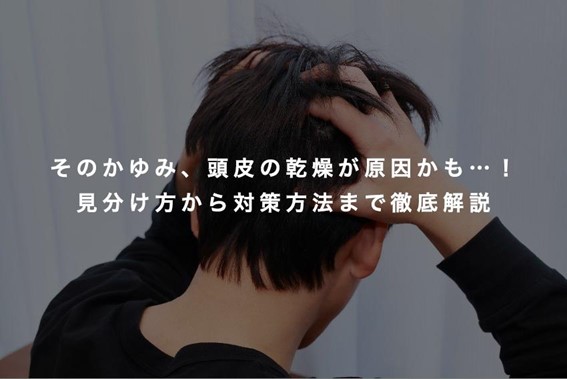
【毛髪診断士監修】男性のフケの主な原因は?対策・予防法や正しいシャンプーの方法も解説
最終更新日:
ファイルが存在しません: ../../usuge/dandruff/index.html
監修者:桜庭 翔
フケとは何か、フケが出る主な原因や疑われる病気についても解説します。また、予防や対策の方法についても紹介しますので、参考にしてみてください。
CHECK

フケの原因は?効果的な対策方法やフケをともなう病気も解説
最終更新日:
2025/05/27
監修者:桜庭 翔
頭皮のフケを改善するには、正しくシャンプーすることと、生活習慣を整えることが重要です。今回は、フケの原因から具体的な対策まで、詳しくご紹介します。
CHECK
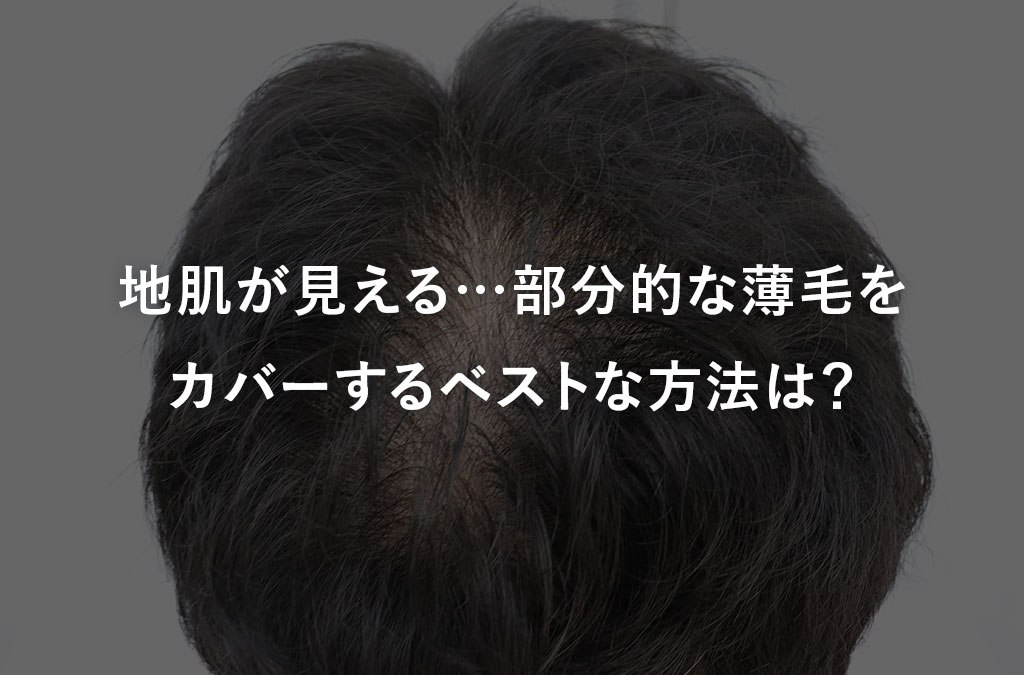
【毛髪診断士監修】地肌が見える…部分的な薄毛をカバーするベストな方法は?
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
「頭頂部の地肌が、透けて見えるようになってきた」「円形脱毛症になった部分が、病後も気になる」など部分的な薄毛についてお悩みの方のために、スカルプDのスタッフがおすすめのカバー方法をご紹介します。
CHECK
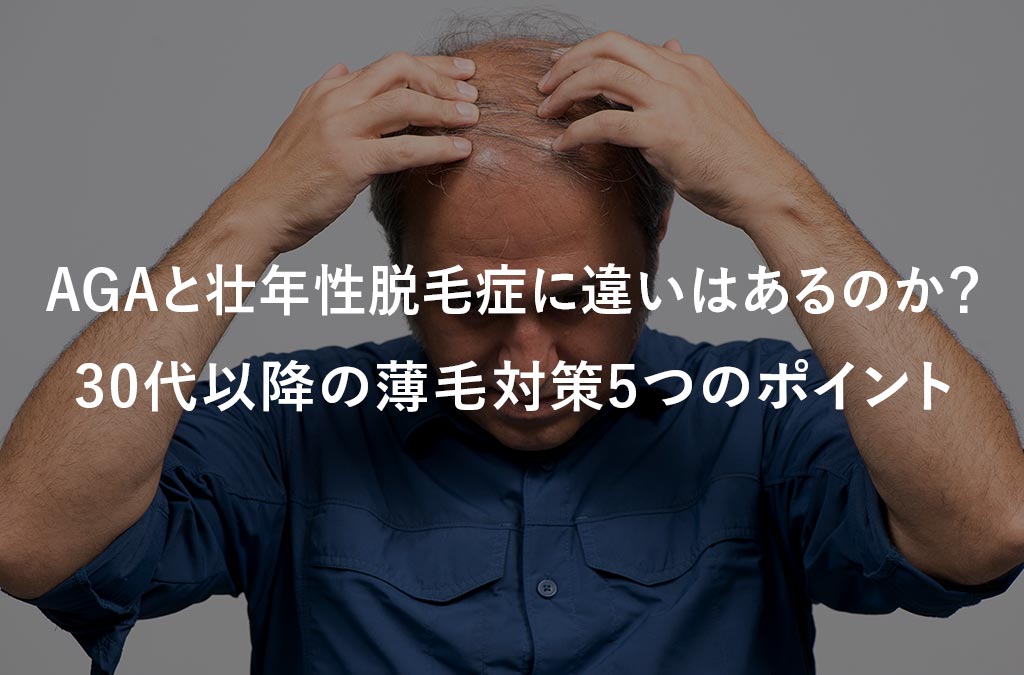
【毛髪診断士監修】AGAと壮年性脱毛症に違いはあるのか?30代以降の薄毛対策5つのポイント
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
主に中年以降の男性に発症する壮年性脱毛症について、メカニズムや対策方法をご紹介します。よく耳にする「AGA」との違いも合わせて解説するので、ぜひご覧ください。
CHECK

【毛髪診断士監修】薄毛の原因と対策を徹底解説!シャンプーや食事改善など今すぐできる方法をご紹介
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
シャンプー方法や効果的な食事、頭皮マッサージなど、気になる薄毛の対策方法について徹底解説していきます。併せて主な薄毛の原因や、年代ごとの薄毛の対策方法についても解説していくので、ぜひ参考にご覧ください。
CHECK
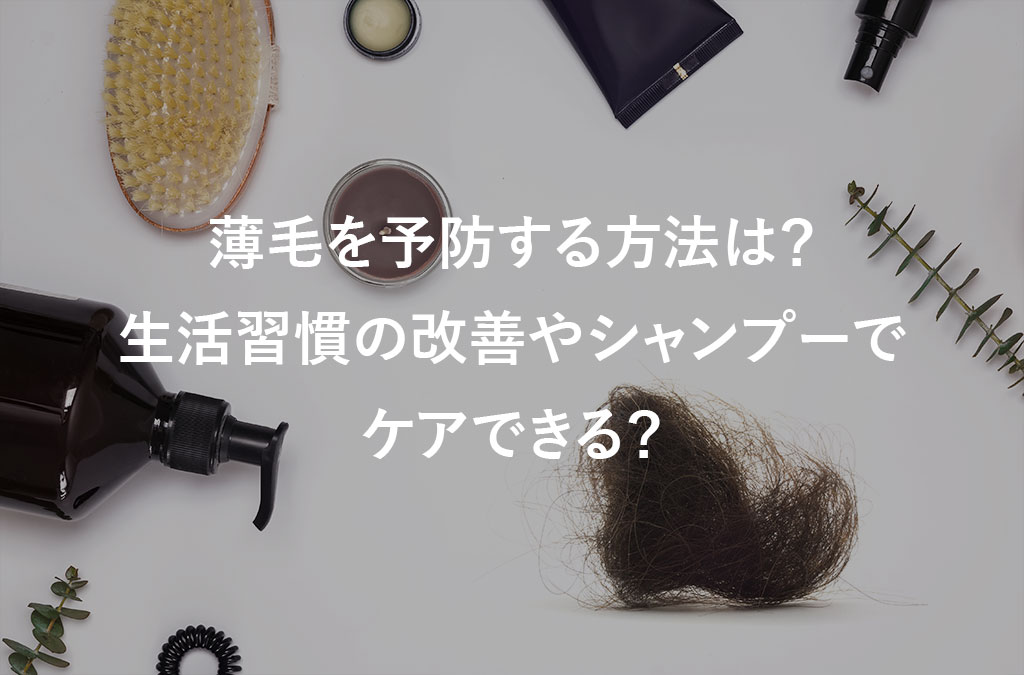
【毛髪診断士監修】薄毛を予防する方法は?生活習慣の改善やシャンプーでケアできる?
最終更新日:
ファイルが存在しません: ../../usuge/usuge-measures/index.html
監修者:桜庭 翔
薄毛にならないためには、まず原因を正しく知ることが大切です。今の自分の状態を知りたい方は、ぜひ【危険な抜け毛&頭皮チェック】を。生活習慣の見直しや、抜け毛対策に効果的なシャンプーの選び方についてお伝えします。
CHECK

【毛髪診断士監修】富士額とM字型の薄毛(ハゲ)には【違い】がある2つの見分け方とは
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
富士額とM字型の薄毛の違いと、その見分け方について紹介します。
CHECK
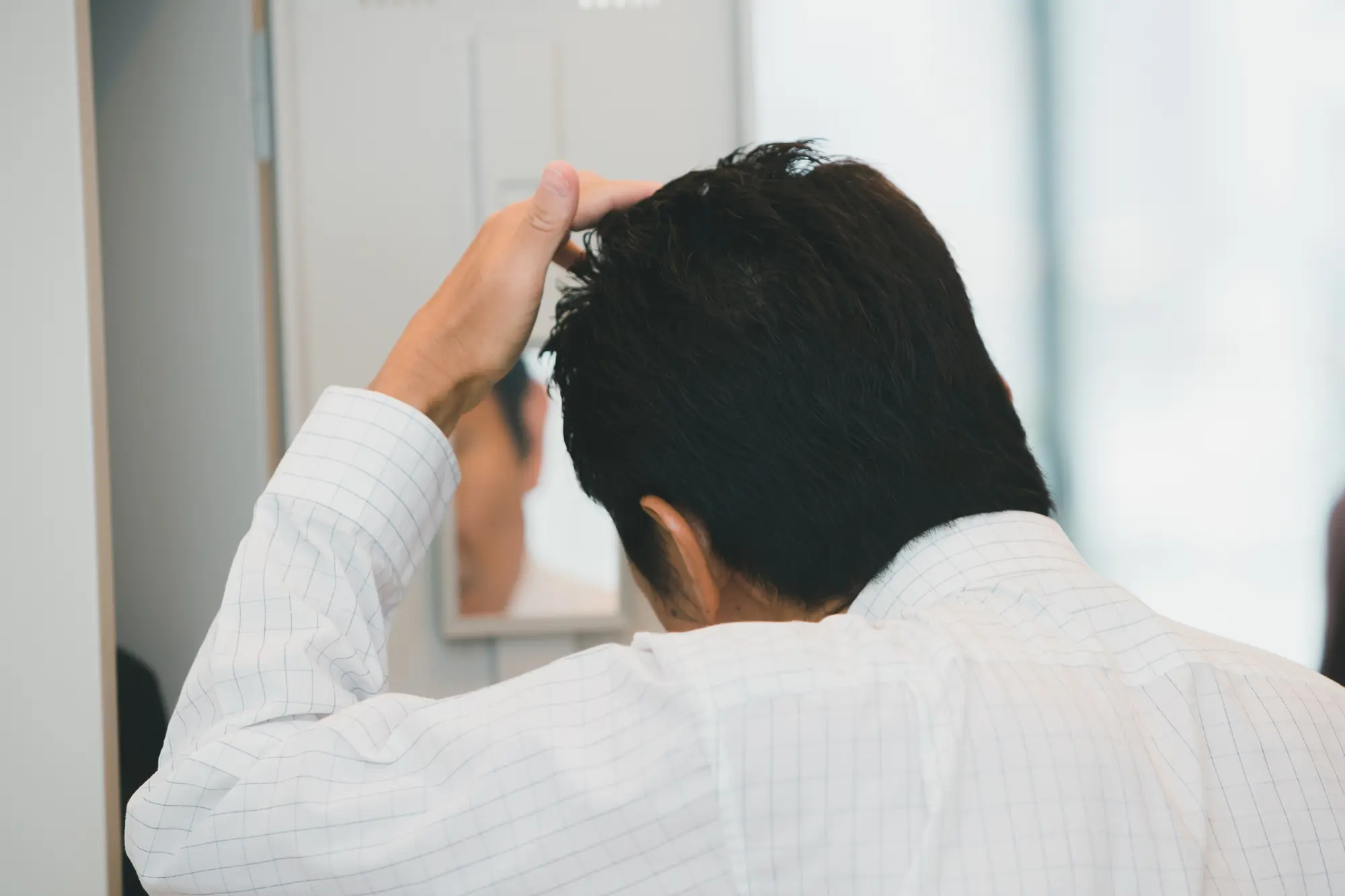
【毛髪診断士監修】【危険】枝毛が薄毛(ハゲ)進行のサイン!?男性が枝毛になる原因4選
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
薄毛(ハゲ)予防のためにも、枝毛を見つけたら対策が必要です。枝毛ができる4つの原因と対策方法をご紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】高校生が薄毛(ハゲ)になる原因とは?今からできる6つの対策法
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
高校生でも薄毛になる原因や薄毛の分類、改善方法についてご紹介します。早めの対策で、健康な髪の毛を保ちましょう。
CHECK

【毛髪診断士監修】納豆が薄毛にいいって本当? 納豆がもたらす髪への影響
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
納豆に含まれる成分はどのような効果があるのか、それらに薄毛を引き起こす原因はあるのかを詳しく検証しました。
CHECK

【毛髪診断士監修】知らなくて平気?薄毛(ハゲ)を招く間違った糖質制限
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
糖質制限をしたいなら、正しい方法を理解してから行なうことが大切です。そこで糖質の不足・過剰による髪や身体への弊害と、正しい糖質制限の方法についてまとめました。
CHECK

【毛髪診断士監修】髪がパサパサな男は薄毛(ハゲ)になりやすい 夏と冬に要注意
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
「髪のパサつきは何が原因か、どうすればパサつきを治せるか」。これらの2点を中心に解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】毛根から血が出る理由 髪を抜くと薄毛(ハゲ)に影響するのか?
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
髪を抜くとまれに出血する理由や、出血が引き金になる皮膚トラブルの説明を通して、髪を引き抜くことの危険性を知りましょう。
CHECK

【毛髪診断士監修】「髪が細いとハゲる」はウソ!?髪の太さと薄毛の関係、毛を太くする方法
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
太い毛と細い毛の見分け方や、細い毛を太くする方法について紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】湯シャンでワックスは落とせる?薄毛を予防するための髪の洗い方
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
湯シャンのメリットや、ワックスを使った日の洗髪方法など、頭皮にやさしい洗い方を紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】毛先の細い抜け毛が増えたら薄毛(ハゲ)進行のサイン
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
なぜ髪の成長に異常が起こるのでしょうか。そして、毛先が細い抜け毛が増えたときに有効な薄毛対策についてもご説明します。
CHECK

【毛髪診断士監修】生卵で薄毛(はげ)になる?1日に何個まで食べて良いのか
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
生卵を食べることと薄毛(はげ)には、どのような関係があるのでしょうか。生卵を安心して食べるためにも、その噂の真偽を確かめておきましょう。
CHECK

【毛髪診断士監修】寝癖が原因で薄毛(ハゲ)になる? 寝癖の原因と直し方を知ろう!
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
どうして寝癖ができるか、どうすれば寝癖を予防できるかを解説し、寝ぐせと薄毛リスクとの関係も解き明かします。
CHECK

【毛髪診断士監修】気になるつむじ割れ…将来薄毛(ハゲ)の原因になるかも?
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
つむじ割れの原因や対処法を知り、薄毛のリスクを減らしましょう。
CHECK

【毛髪診断士監修】生まれつきの猫っ毛は薄毛につながる?
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
猫っ毛とはどのようなものなのか?原因や対策についても解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】タンパク質不足で薄毛(ハゲ)に!プロテインで髪は育つのか?
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
タンパク質が髪に変わる流れや、薄毛対策に適したプロテインの選び方、プリテインを飲むタイミングをご紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】薄毛におすすめワックスは?ボリュームの出し方や付け方も解説!
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
「薄毛におすすめのワックスの種類は?」「ボリュームを出せるつけ方は?」など、薄毛で、ワックスについて詳しく知りたい人のために、ワックスについてのよくある疑問を解説します。
CHECK

【毛髪診断士監修】側頭部の薄毛(ハゲ)原因はAGAじゃなかった!症状別の効果的な改善策
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
側頭部の薄毛の原因が甲状腺やAGA以外の脱毛症が関わる理由と、改善策をご紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】おでこが広くなったと感じたら…日常生活を見直しおでこ拡大を防ぐ!
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
AGA以外でおでこが広くなる原因と、育毛剤を使った対策方法を紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】短くて細い毛は薄毛の始まりかも?短い抜け毛の原因と減らす方法
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
ヘルメットをかぶるとはげる可能性が高くなる理由として、摩擦、蒸れ、雑菌と3つが挙げられます。それぞれについて、詳しく検証します。
CHECK

【毛髪診断士監修】眠りながらヘアケアできる?ナイトキャップの効果と選び方
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
ナイトキャップの基礎知識や、効果についてご紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】薄毛に似合う髪型は坊主?メンズの薄毛が目立つ髪型・目立たない髪型
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
「薄毛でも似合う髪型ってある?」「薄毛が目立たないスタイリング方法は?」と薄毛の人でヘアスタイルに悩む人は多いのではないでしょうか。そこで今回は、薄毛が目立たない髪型を写真付きで紹介します。
CHECK

【毛髪診断士監修】薄毛でもパーマをかけていい?注意点やパーマが似合う薄毛タイプを紹介
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
薄毛の人がパーマをかける際の注意点や、パーマが似合う薄毛タイプをご紹介します。また、薄毛のメンズに似合う髪型も解説。
CHECK

【毛髪診断士監修】薄毛は睡眠で治る?関係ない?育毛のための睡眠の考え方
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
睡眠不足は髪の毛の成長にも悪影響をおよぼす可能性があります。この記事では睡眠と薄毛の関係について解説します
CHECK

【毛髪診断士監修】脂漏性脱毛症の症状・原因・治療は?対策にはシャンプーや育毛剤が重要
最終更新日:
2025/03/04
監修者:桜庭 翔
この記事では脂漏性脱毛症の症状や特徴、発症する原因、予防するためのセルフケアについて詳しく解説します。
CHECK